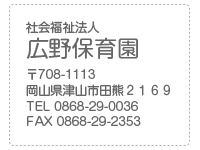KIDSダイアリー
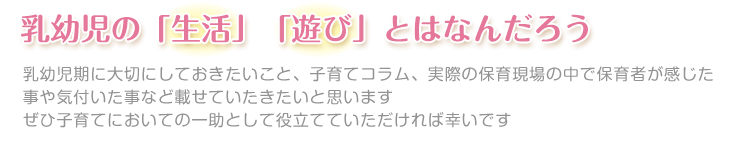
- R8年度 採用情報(新卒・中途)
- R8年度から、私たちと一緒に保育の仕事をしませんか?
正職員保育士を1名募集しています!!
1年目、2年目は優しい先輩保育士が当園の保育についてわかりやすく指導いたします。
2年目から主担任をうけもってバリバリ保育の仕事を楽しんでいる職員もいます。
職員は園の宝です。園長先生をはじめ、私たちは楽しく保育ができる環境づくりを目指しています。
ぜひ、ご応募おまちしております!! 見学、ボランティアも随時受け付けています。
℡:0868-29-0036 担当:佐々木 - 2024/09/28
- 食事はバイキングゥグゥグッド!!
- 「その野菜は少なめで」「ごはんは大盛り!!」昼食時になると、子どもたちのそんな声が聴こえてきます。
当園では3歳以上の食事はバイキングです。
バイキングといっても給食の先生が配膳台に立って、子ども一人ひとりに食べたい量を聞いてお皿に盛りつけをし
ます。
少なめにしてもらった子どもでも、まだ食べれそうならおかわりしにきます。
「食べてみたらおいしかったけん」こんなやりとりもしょっちゅうです。
子どもたちが保育者の指示によって、一斉に食事をして、決められた時間までにたべるようにせかされることもあ
りません。
お腹がすいて、食べたくなったこどもから配膳台にやってきます。
子どもは、好きな時間に好きな友達と好きな場所で食事をします。
みんな一斉に同じ量盛り付けられた食事をしていた時は残食がありましたが、今では残食ゼロです。
バイキングのねらいは、「食への意欲を高める」「食に関心を持つ」「完食の達成感」などありますが、いちばん
のねらいは「選ぶこと」。子どもが自ら選ぶことです。遊びも食事も子ども主体。食事中は笑顔が絶えません。
これからも子どもたちが楽しく食事ができる環境をつくっていきたいと思います。
子どもたちも職員もバイキングゥグゥグッド!!
- 2024/04/16
- Q.失敗するとすぐにあきらめてします。どうすればいいですか?
- A.小さな「できた!」を増やすことが子どもの自信や意欲につながります
大人にとっては一見簡単な動作も子どもには複雑な動きの連続で、うまくいかない、取り組めないことがあります。例えば三輪車の場合、もう2歳なら乗れるだろうと思っていても、まだ2歳の子どもにとっては右左を交互に上げ下げすることは至難の業です。もちろん個人差はありますが。
「こっちの足をペダルにのせてこぐだけでしょ!」「やればできるからやってごらん!」と伝えたところで、その時点で」できないことを望んでもまだまだ本にとっては難しいことなのです。しつこく言いすぎると、せっかく三輪車に関心が向いていたのに、乗ることをあきらめてしまうでしょう。「(ペダルに足をこげていなくても)ここまで頑張って乗れてこれたね」と認めます。周りのお子さんを見ると、「あれもこれも皆でできている」と焦りそうになりますが、一つひとつ、一歩一歩でいいんです。子どもが今頑張れている課題があれば、それ意外のことは大目に見てあげてもいいでしょう。成功体験を増やして。褒められる認められるチャンスを作ることが子どもの自信につながり大事なことです。そんなときには、課題の過程や量、動きや茶道工程を細かく分けて、達成しやすいようにスモールステップにしてあげると「できた!」を具痩せます。例えば縄跳びの練習は「その場で跳ぶ」「縄をまわす」を別々にします。そして「縄を回しながらまたぐ」「一回だけ跳ぶ」‥と、細かく課題を分けることで、複雑な動きもできるようになります。三輪車、縄跳び、跳び箱、製作‥。また、遊びの中で気づいたことや発見したことでもいいと思います。なんでも小さなステップから、一つひとつやっていき、その都度ほめていきます。課題をしぼって、なるべく一つひとつ「できた!」を実感してから、次のステップに登れるように、こちらもハードルをさげてあげると、ちょっぴり不器用な子にも、だんだんと自信をつけてあげることができます。できているところ、頑張れているところにフォーカスし、一つひとつ褒めて認めることで、自信や意欲を持つことができるでしょう。 - 2024/01/26
- お空ってどうして昼は青くて、夜は黒いの?
夕方暗くなってきた頃、年長児の女の子がこんな質問をしてきました。
「ねぇ先生、空って不思議じゃない?」
「どうして?」
「だって昼はあんなに青いのに、お日様が沈んでくると、今度はオレンジ色になって、その後真っ黒になるでし
ょ。」
「ほんとだね。どうしてなんだろうね。」
「う~ん、もしかしたら、お日様が絵具で空を塗ってるのかなぁ~。」
「そうかも。ほんとにそうだったら太陽は絵描き屋さんだね。」
「だったら、どうして青とオレンジと黒色しか使わないんだろう…。私の絵の具でよかったら貸してあげるの
に。」
この女の子は、お日様が本当に空の色を塗っているんだと信じているようでした。そうしないと、彼女の頭の中
でひらめいた問いが解決できなかったからでしょう。大人になったら「なぜ空の色が青いのか、夜になったら黒
いのか」なんて気にしなくなるのに、子どもって本当に大人が想ってもみないことを疑問に思ったり、感じたり
してるんだなと思いました。
子どもって本物の哲学者ですね!!
- 2022/11/14
- 職業ランキング?
-
底辺職業ランキングで批判が殺到しているというニュースをテレビで見ました。底辺職業と聞いただけで、どうも
違和感を感じたのでありますが、誰が何のために職業にランキングを決めたのだろうと思います。
そして、テレビにうつされたそのランキングを上から何気に見ていると、見覚えの漢字が通り過ぎる。「ん?」と
目を凝らして見てみると「保育士」がランキングに入っている。保育士…職業…底辺…。なぜ…?
私は保育士という職業ほどやりがいのある仕事はないと心から思っているのですが、それを“底辺”に位置づけた人
は保育士という職業をどのように考えているのでしょうか。底辺職の特徴として次の三つが挙げられているとのこ
とです。①肉体労働である②誰でもできる仕事である③同じことの繰り返しであることが多い
① の肉体労働であるは否めないかもしれないが、②と③の特徴については全く意味がわからない。
そもそも保育士という仕事は、2年間あるいは4年間専門的な勉強をし、国家資格を要する職業である。ただの子
守りであれば誰にでもできるのかもしれませんが、保育士は子育てのプロフェッショナルです。誰にでもできる職
業ではありませんし、同じことの繰り返しでできる仕事ではありません。このような根も葉もないメディアでの報
道によって、さらに保育士という職業へのイメージダウンを加速させてしまいかねないことを願うばかりです。保
育士不足、少子化問題、待機児童に歯止めをかけるには、国を挙げて保育という仕事の重要性をもっと発信してい
ただきたいし、保育士という職業の社会的な補償レベルを上げて欲しいと思います。最初に戻りますが、どの職業
も社会に必要にされているから存在するのであり、このようなランキング付けをすること事態がナンセンスだと思
います。力の入れどころの優先順位を誤って、この先もずっともたもたしていたら、そのうち日本は世界からも後
れをとる発展途上国になってしまうのも近い未来なような気がしてなりません。
- 2022/07/13
- もう少しのしんぼうだよ
-
コロナ禍になって2年。
マスク生活もだいぶ慣れてきたようですが、声を出したり、体を動かすとやっぱりしんどい…。子どもたちも少な
からず息苦しさを感じているはず。早くマスク生活から脱却したい。
つらい時悲しいときはマスク外していいんだよ。」
「外遊びのときはマスク外していいんだよ。」
「飛び上がるほど嬉しいときもマスク外していいんだよ」って言ってあげたいけど、それができないことがもどか
しくて仕方がない。
マスク外して、子どもたちと思いきり口を開けて笑いあえたらどれだけ楽しいだろうね。
これだけは、いまだに慣れることのできない悩みごとの一つ。
それでも、今日も朝から子どもたちはマスクをして元気に歌を歌っている。
「幸せなら手をたたこう」の歌。
脱マスク生活まで、もうあと少しであることを信じて乗り越えよう。
- 2022/05/12
- コロナ禍の夏祭り!!
-
コロナ禍で、昨年度に続き、今年度もお涼み会が中止となりました。年に一回、子どもたちが心待ちにしている夏のイベントです。それでも夏祭りの雰囲気だけでもなんとか体験させてあげたいという思いから、園児・職員・父母の会役員のみで、夏祭りごっこをしました。まずは盆踊りからスタート!!アンパンマン音頭や元気音頭を踊りました。出店は、ヨーヨー釣り、くじ引き、ジュース屋。それに加えて、年長児は的あてゲームのお店を出しました。お店の看板や、ちょうちんも年長児の手作り。この日、子どもたちは、甚平、浴衣を身にまとい、雰囲気作りもバッチリ。引き換え券をもって、自分のいきたい出店に仲のいい友達と手をつないでルンルンで歩いていく姿を見ることができました。ほんのささやかな夏祭りでしたが、子どもたちにとってはワクワクしっぱなしのひと時を堪能できたのではないかと思います。お涼み会の中止はやむ負えませんでしたが、何もかも中止にしてしまうのではなく、少しやり方を工夫することで子ども主体の夏祭りを楽しむことができました。
父母の会々長をはじめ、役員皆さんのご協力のおかげで、今年も子どもたちのために夏祭りを実現することができましたこと心より感謝申し上げます。

- 2021/07/19
- 乳幼児期の教育ってどんなこと?
乳幼児期の教育って何?保育園って何を教えてくれるところですか?といった問い合わせがちょこちょこあります。一言でいえば、幼児教育とは「教える」というよりも子どもの”よさ”を見つけることです。先に申し上げておきますが、保育はできるできないで子どもを評価することではありません。また、子どもの技術の向上を第一に目指すことでもありません。目に見えることよりも、むしろ目に見えないところに焦点をあてて子どもの育ちを見ていくことが保育の大前提にあるからですである。さらに言えば、学校教育と決定的に違うのは、時間割がないということではないでしょうか。保育園は、小学校生活6年間を乗り越える力を身につけることが目標ではありません。もちろん保幼小の接続は、スムーズに学習期に移行していくために大切なことです。それよりも、この先の10年20年先を見据え、生きる力をつけることこそが幼児教育なのである。従って、すぐにその結果の芽は出てはきませんが、長い月日を経て、芽をだしてくるものであると考えています。失敗や困った体験、葛藤体験や感動体験、これらの体験を通して、自分はどういう人間になりたいのか、どういうことが恥ずかしいことなのかを学ぶことができます。生きる喜びを知ったり、価値観や人生観学んでいく場であると思っています。だからこそ、子どもが自主的に活動できるよう自由を与え、一人ひとりどんな子どもなのかを見極めていくために保育者がいるといっても過言ではありません。困っている人に声をかける子ども、友達の失敗を笑う子ども、どうしても勝ちたいからじゃんけんで後出しする子ども、様々な子どもの姿を見ることができます。肝心なのはその時に、保育者がどう子どもにどうアプローチしていくか?が重要になります。自分のしたことがどういうことなのかを気づかせること。保育者自身に、こんな子どもに育ってほしいという願いがないと、保育者のいる意味は正直ないと言えましょう。言われたことを言われたとおりにできる子どもが”おりこうさんね”と評価される時代はもうとうの昔に終わりました。そのようなことはこれからの時代、ロボットがすべて代わってしてくれるでしょう。これからは自分が主体となりで、自分で妥当性のある答えを生み出していく力、また創造していく力が求められます。目に見える結果がすべてではありません。子どもが日々どんな心もちで生活を送っているのか?結果ではなく過程にこそ子どもの育ちがあるのであることを我々保育者は知っておく必要があります。再度申し上げますが、子どもの育ちを支え、子どもの”よさ”を引き出していくことが幼児教育なのです。
- 2021/06/30
- G・W VS 新型コロナウイルス
-
明日からいよいよゴールデンウイークのはじまりです。5月病の幕開けともいう。
全国ならず岡山県内でも新型コロナウイルス感染症が、広がりつつある中で迎えるゴールデンウイーク。
やむを得ずSTAY HOME? or どこかへ外出する?
園長「はぁ~、神様これっていつ収束するのでしょうか?」
神様「はい、それは誰にもわかりません」
園長「では神様、どうすれば収束するのでしょうか?」
神様「はい、それも誰にもわかりません」
園長「では、いったいどうすればいいのでしょうか」
神様「はい、すべてはあなた方の行動次第です」
- 2021/04/30
- 令和3年度 進級式!!
今日は先生と子どもだけの進級式。
青い制服を着て、あお組(年長児)が出し物を考えた。
歌を歌ったり、ダンスをしたり、外で鬼ごっこをしたり…。
子どもが企画し考えた子ども主体の進級式。困ったときは先生の助け舟をかりながらも、年
長児としての自覚をもつことができたように思う。
一年で心も身体もこんなに成長するんだと喜ばしく感じる瞬間。
いやいや、そんな感慨にひたっている場合じゃない。
大人だってー、日々精進!!
ということで、ひとまず本日はご進級おめでとうございました<(_ _)>
- 2021/04/16