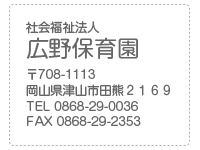KIDSダイアリー
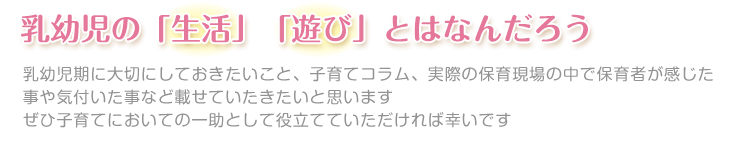
- 職業ランキング?
-
底辺職業ランキングで批判が殺到しているというニュースをテレビで見ました。底辺職業と聞いただけで、どうも
違和感を感じたのでありますが、誰が何のために職業にランキングを決めたのだろうと思います。
そして、テレビにうつされたそのランキングを上から何気に見ていると、見覚えの漢字が通り過ぎる。「ん?」と
目を凝らして見てみると「保育士」がランキングに入っている。保育士…職業…底辺…。なぜ…?
私は保育士という職業ほどやりがいのある仕事はないと心から思っているのですが、それを“底辺”に位置づけた人
は保育士という職業をどのように考えているのでしょうか。底辺職の特徴として次の三つが挙げられているとのこ
とです。①肉体労働である②誰でもできる仕事である③同じことの繰り返しであることが多い
① の肉体労働であるは否めないかもしれないが、②と③の特徴については全く意味がわからない。
そもそも保育士という仕事は、2年間あるいは4年間専門的な勉強をし、国家資格を要する職業である。ただの子
守りであれば誰にでもできるのかもしれませんが、保育士は子育てのプロフェッショナルです。誰にでもできる職
業ではありませんし、同じことの繰り返しでできる仕事ではありません。このような根も葉もないメディアでの報
道によって、さらに保育士という職業へのイメージダウンを加速させてしまいかねないことを願うばかりです。保
育士不足、少子化問題、待機児童に歯止めをかけるには、国を挙げて保育という仕事の重要性をもっと発信してい
ただきたいし、保育士という職業の社会的な補償レベルを上げて欲しいと思います。最初に戻りますが、どの職業
も社会に必要にされているから存在するのであり、このようなランキング付けをすること事態がナンセンスだと思
います。力の入れどころの優先順位を誤って、この先もずっともたもたしていたら、そのうち日本は世界からも後
れをとる発展途上国になってしまうのも近い未来なような気がしてなりません。
- 2022/07/13
- 乳幼児期の教育ってどんなこと?
乳幼児期の教育って何?保育園って何を教えてくれるところですか?といった問い合わせがちょこちょこあります。一言でいえば、幼児教育とは「教える」というよりも子どもの”よさ”を見つけることです。先に申し上げておきますが、保育はできるできないで子どもを評価することではありません。また、子どもの技術の向上を第一に目指すことでもありません。目に見えることよりも、むしろ目に見えないところに焦点をあてて子どもの育ちを見ていくことが保育の大前提にあるからですである。さらに言えば、学校教育と決定的に違うのは、時間割がないということではないでしょうか。保育園は、小学校生活6年間を乗り越える力を身につけることが目標ではありません。もちろん保幼小の接続は、スムーズに学習期に移行していくために大切なことです。それよりも、この先の10年20年先を見据え、生きる力をつけることこそが幼児教育なのである。従って、すぐにその結果の芽は出てはきませんが、長い月日を経て、芽をだしてくるものであると考えています。失敗や困った体験、葛藤体験や感動体験、これらの体験を通して、自分はどういう人間になりたいのか、どういうことが恥ずかしいことなのかを学ぶことができます。生きる喜びを知ったり、価値観や人生観学んでいく場であると思っています。だからこそ、子どもが自主的に活動できるよう自由を与え、一人ひとりどんな子どもなのかを見極めていくために保育者がいるといっても過言ではありません。困っている人に声をかける子ども、友達の失敗を笑う子ども、どうしても勝ちたいからじゃんけんで後出しする子ども、様々な子どもの姿を見ることができます。肝心なのはその時に、保育者がどう子どもにどうアプローチしていくか?が重要になります。自分のしたことがどういうことなのかを気づかせること。保育者自身に、こんな子どもに育ってほしいという願いがないと、保育者のいる意味は正直ないと言えましょう。言われたことを言われたとおりにできる子どもが”おりこうさんね”と評価される時代はもうとうの昔に終わりました。そのようなことはこれからの時代、ロボットがすべて代わってしてくれるでしょう。これからは自分が主体となりで、自分で妥当性のある答えを生み出していく力、また創造していく力が求められます。目に見える結果がすべてではありません。子どもが日々どんな心もちで生活を送っているのか?結果ではなく過程にこそ子どもの育ちがあるのであることを我々保育者は知っておく必要があります。再度申し上げますが、子どもの育ちを支え、子どもの”よさ”を引き出していくことが幼児教育なのです。
- 2021/06/30
- G・W VS 新型コロナウイルス
-
明日からいよいよゴールデンウイークのはじまりです。5月病の幕開けともいう。
全国ならず岡山県内でも新型コロナウイルス感染症が、広がりつつある中で迎えるゴールデンウイーク。
やむを得ずSTAY HOME? or どこかへ外出する?
園長「はぁ~、神様これっていつ収束するのでしょうか?」
神様「はい、それは誰にもわかりません」
園長「では神様、どうすれば収束するのでしょうか?」
神様「はい、それも誰にもわかりません」
園長「では、いったいどうすればいいのでしょうか」
神様「はい、すべてはあなた方の行動次第です」
- 2021/04/30
- コロナ禍の今、私たちに求められること
-
令和3年度がスタートしました!
昨年度は、新型コロナウイルス感染症のため、この得体のしれないウイルスを「もらっちゃいけない」「うつしち
ゃいけない」ということで、ほとんどの行事を中止または縮小せざる負えませんでした。
マスク着用を余儀なくされ、人と人との距離を保たなければならない。
「ほんとにやっかいなウイルス」
子どものために一番いいことをしたいと思っているのに、それが実現しずらい。
だけど、子どもたちが保育園に来てくれる以上、あれもこれもできないなんて言ってられない。
「できない」を「できる」へ変えていこう。
今までと同じでなくてもいい。方法を変えれば、「できる」へ変えられる。
一番変えなければいけないのは、いまままで当たり前だと思って過ごしてきた私たちの先入観。
それでも子どもたちは、楽しんでるように見える。それが唯一の救い?
もっと頭を柔軟にして、ピンチをチャンスに変える力。考える力。想像力。
今一番、私たち保育者に求められていること。
先の事ばかり考えるのはいったんやめにして、今目の前にいる子どもたちとしっかり向き合っていこう。
- 2021/04/06
- 3時のおやつはかき氷屋さんごっこ
- 昨日のおやつは子どもたちが大好きなかき氷屋さんでした。順番にならんでいればもらえるのですがどうも物足りない。
”よし!今日はかき氷屋さんにしよう”
「いらっしゃいませーいらっしゃいませー!今日のかき氷は300円になります。100円玉の数に限りがありますので、あお組さんは100円玉を使わないようにお願いします」
つまり、あお組は50円玉と10円玉で300円の買い物をしなければなりません。
遠くの方から「300円いるんだって!」「お金とりにいこうや!」などの声が聞こえてきます。
お金はもちろん現金ではなく画用紙で作った手作りのお金です。
かき氷や差の前はアッとの言う間に長蛇の列ができました。
「はい、300円ちょうどいただきます。毎度ありです!!」
嬉しそうにかき氷を手にして部屋へともどっていくもも組(年少児)とみどり組(年中児)
一番困ったのはあお組です。
「50円玉2枚で100えんじゃろ…あと一枚50円で…300円?とりあえず並んでみる!!」
長い長い順番を待ってやっと自分の番が回ってきました。
「いらっしゃいませー!えーっと50円玉が1,2,3枚で150円ですね。こちらのかき氷は300円です。お客さんお金が足りません」
再度出直しです。
「いらっしゃいませー!10円ばかりにしたんだね。かぞえてみるよ。10、20、30…280.280円?あれ!お金が足りませんよ」
またまた出直しです。でもあお組(年長児)の子どもたちはへこたれません。
だってかき氷の為ですから(笑)こちらも、最後まで自分の力でやりとげて大きな達成感を味わってほしい…そんな願いから心を鬼にしました。
Sくんは、4回目にしてやっと300円を払ってかき氷を買うことが出来ました。
「毎度あり!!ちょうどいただきます」Sくんは大きく息を吸い込んだ後に「やったー!!」と何度も飛び跳ねて喜びました。その姿は目にやきついて離れませんね。
生活・遊びの中に教育をもっていく。これが幼児教育であると考えています。今回も必要感を感じ意欲的にチャレンジする姿を見ることが出来ました。生活・遊びをとおして、たくさんの学びが得られる機会をこれからも作っていきたいと思います。
あお組のこどもたちよ!! これからもたくさんの試練を乗り越えて たくましくあれ!!



- 2019/08/22